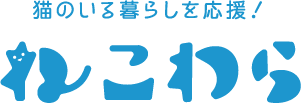猫って本当に器用で身体能力も高いですよね。
中にはドアを難なく開けてしまう猫もいます。
実際、猫ほどのジャンプ力があれば、ドアは簡単に開いてしまいます。
今回は猫にドアを開けられないようにする防止対策を紹介していきます。
目次
猫はドアを開けてしまう!
猫はその驚異的な脚力と、頭の良さから上の動画のように扉をいとも簡単に開けてしまいます。
扉の種類も様々ですが、スライド式のドアも押し戸、引き戸も関係なく開けてしまう猫もいます。
飼い主さんの中には、どうしても猫に入ってほしくない部屋もあるのではないでしょうか。
何か大切なものがあったり、寝室も人によっては入ってほしくないかもしれません。
また、餌が入っている棚を猫が開けてしまうからやめさせたいなんてこともあるかもしれません。
そこで、猫がドアを開かないようにするための8つの防止策を紹介していきます。
ドアを開ける猫への8つの防止対策!
ドアを開けてしまう猫への防止対策として以下の8つが挙げられます。
- 猫の苦手な匂いで遠ざける
- マジックテープの利用
- 磁石の利用
- ドアストッパーの利用
- ドアノブ方向を変える
- 鍵の設置
- 紐の利用
- ドア開き防止専用道具の利用
1つずつ詳しく見てみましょう。
1.猫の苦手な匂いで遠ざける
特定の部屋にのみ猫を入れたくない場合、猫の嫌いな匂いをさせることで入らないようにすることができます。
例えば猫の苦手なコーヒーの匂いや柑橘系の匂いのする芳香剤を置いて、入らないようにします。
柑橘系の芳香剤は、100円ショップでも売っているためとても簡単な予防方法です。
ただ物理的に防げるわけではないため、匂いをあまり気にしない猫にとっては効果が薄いかもしれません。
2.マジックテープの利用

猫がドアを開ける際にはジャンプして、ドアノブを下げてしまうことでドアが開きます。
ただ押したり引いたりする力自体はかなり弱いため、ドアと壁の間にマジックテープをくっつけておきます。
こうすることでドアノブが下がっても、マジックテープ同士がくっついているため簡単には開かないようになります。
3.磁石の利用
磁石もマジックテープと仕組みはほとんど同じです。
ドアと壁それぞれにテープなどを利用して磁石をくっつけておきます。
マジックテープと同じように、ドアノブが開いても簡単にはドアが開かなくなります。
4.ドアストッパーの利用
アイメディア ストロングドアストッパー
ドアの下の部分にドアストッパーを付けておきます。
ストッパーを立てておくことで、ドアノブを下げても簡単に扉は開かなくなります。
設置も簡単で、手間もそれほどかからないためかなりおすすめです。
5.ドアノブ方向を変える

多少手間はかかりますが、ドアノブの方向を変えるのも一つの手です。
基本的にドアノブは画像のように水平の方向を向いていますが、取っ手の部分が通常上を向くようにしておくのです。
ドアノブの方向が水平ではなくなることで、猫もドアを開けるためにジャンプをする際に自分の体重をかけることができなくなります。
ただこの方法は猫が慣れてくることによって、突破されてしまうことも多いようです。

6.鍵の設置

ドアにカギを付けることで猫の侵入を防ぎます。
鍵といっても大層なものではなく、画像のようなフックに掛け金が引っかかるようなタイプのものです。
こういったタイプの鍵の設置はスライド式のドアでも簡単にできます。
7.紐の利用
ドアにひもをつけてほかの場所に結んでおきます。
この方法はかなり強力ではありますが、部屋に入るためにいちいち紐を取らなくてはいけないため、かなりめんどくさいのが弱点です。
またビニール紐などを使っている場合、猫は簡単に紐自体を壊してしまいます。
そうなることがないように紐の素材も気を付ける必要があります。
8.ドア開き防止専用道具の利用
上記で挙げた方法以外にも、猫用のドア開き防止道具も様々な種類のものが販売されています。
こちらはドアレバーの下に設置することでドアロックできるようになる商品です。
お子さんがいらっしゃるご家庭では、イタズラでドアを開けたままロックして閉めてしまうケースもあるようなので、外側に設置するなどの工夫が求められるかも知れません。
また、粘着テープはヘアドライヤーなどで温めればきれいにはがせるそうです。家具を傷めたり、壊すことがないので安心ですね。
まとめ
猫は身体能力が高くとても器用なため、勝手にドアを開けてしまう子もいます。
どうしても開けてほしくないドアがある場合は、開けられないように防止策を取りましょう。
具体的な防止策は以下の8つになります。
- 猫の苦手な匂いで遠ざける
- マジックテープの利用
- 磁石の利用
- ドアストッパーの利用
- ドアノブ方向を変える
- 鍵の設置
- 紐の利用
- ドア開き防止専用道具の利用
ぜひ試してみてください!
また、脱走対策もこれと近いものがあるので、気になる方は是非チェックしてみてください!
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。