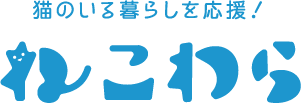6~9月頃は蚊が多くてほんとに嫌になりますよね。
耳元でプ~ンと聞こえると、うっとうしくて仕方がないものです。
ただ、猫を飼ってると単に不快なだけではなく、「蚊に刺されて大丈夫なのかな?」と想ったりしませんか?
そこで今回は猫が蚊に刺されることの注意点と、猫のいるお家でもできる蚊の対策について紹介していきます!
猫も蚊に吸われる!刺されて大丈夫なの?
短毛猫・長毛猫関係なく、猫は蚊に刺されます。
長毛種などは毛量が多いから大丈夫だと思われがちですが、猫が刺される場所として多いのは、耳や鼻などの毛が薄い場所が多いようです。
気になるのはその症状ですよね。
先に言っておくと、基本的には蚊に刺されても大丈夫なようです。
人間と同じように、かゆみが出ることもあるようですが、これ自体は正直ほとんど気にする必要はないみたいです。
もちろん、何かを気になるようなしぐさをずっとしているようであれば、病院に連れていって診てもらいましょう。
そうじゃないと、野良猫なんてたくさん刺される機会ありますしね。
ただ、まれに感染症などを持った蚊がいるのも事実です。
そういった蚊に刺されると、猫は病気になることもあります。
猫が蚊によって感染する病気とは?
実は猫が蚊によって感染する病気の種類は多いようで、よく耳にするものでは「デング熱」や「ジカ熱」などがあります。
ただ、多くの感染症は感染する確率が低いようなのですが、ある2つの病気はそうとも言えず注意する必要があります。
- 蚊アレルギー(蚊刺咬過敏症)
- フィラリア症
蚊アレルギー(蚊刺咬過敏症)
猫の中には、体質的に蚊にアレルギー反応を示してしまう子がいるようです。
そんな子が刺されると出てくるのが、「蚊アレルギー」です。
主な症状としては、刺された場所やそれ以外の場所に発疹(プツプツ)が出てくるようです。
このアレルギーになると、痒みが酷くなり、かきむしることで血が出てしまうケースもあるようです。
猫が何かを気にしているようであれば、早めに見てもらうことをおすすめします。
対策としては、ステロイド剤などを使い、症状を抑えることが多いようです。
猫アレルギーの症状が出ている子の画像はこちらのブログで紹介していたので、気になる方は見てみてください。
フィラリア症
フィラリア症とは、蚊を媒介にして移る寄生虫症です。
見た目は夏場に食べる機会の多い、ソーメンのような感じです。
犬の寄生虫として有名ですが、猫にも移ります。
※フィラリアはかなりグロいため、画像は載せません。興味がある方はこちらの「動画」(かなりグロいです)を参照してみてください。
蚊から入った感染幼虫は猫の体内に侵入すると、皮膚の下などで生活を始め、心臓や肺動脈に寄生されることが多いです。
無症状の例もありますが、主に咳や食欲低下などの症状を見せることが多いです。
ただ、猫の場合は心臓が小さいため、重症化すると突然死のリスクなども出てきます。
そんな物騒なフィラリアですが、ある調査では、猫に感染する割合は、およそ10匹に1匹の割合だと言われています。
意外と多いですよね。
参考:zoetis(リンク切れ)
猫への寄生虫症としては、危険なもののひとつなので、なるべくしっかりと予防したいですね。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

猫の蚊よけ対策3選!
猫の蚊よけは、主に以下の3つの方法で分けられます。
- 猫用網戸の設置
- レボリューションなどの予防薬
- 蚊対策グッズ
猫用網戸の設置
皆さん蚊避け対策として、真っ先に頭に浮かぶのはなんですか?
私の場合「網戸」です。
今でこそ基本クーラーをつけて過ごしていますが、私の実家では、夏は網戸をして扇風機が一般的でした。
網戸は網のほつれなどがなければ、蚊を通さない優秀なフィルターになります。
今では家に入った虫の殺虫スプレーなどもありますが、できれば家自体に入って欲しくないものですよね。
ただ、残念なことに、猫と網戸の相性は悪いです。
そう。爪とぎをしてしまう子が多いのですね。
結果、ほつれた部分から蚊が入ってくるだけではなく、大きいほつれになったら猫が外に行ってしまう危険もあります。
そんな場合に役に立つのが、猫用に強く作られている網戸です。
そんな猫用の強化網戸がほんとに役に立つのか実験している方がいたので、気になる方はそちらをご覧になってください。
ブログはこちら(建材ダイジェスト)
※ザックリ結果を言うと、かなり強い力でなければ、ほとんどほつれにはならないようです。
ただ、考え方次第にはなりますが、100%蚊の侵入を防げるというものではないと思います。
どちらかというと、脱走防止としての猫用網戸はおすすめかもしれませんね。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
ブロードラインやレボリューションなどの予防薬の使用

ブロードラインやレボリューションはご存知ですか?
猫の首元にポタっと垂らすことで、気軽に寄生虫予防が出るスポット薬です。
ノミやダニ、蚊を媒介にして移るフィラリアなどの寄生虫予防として抜群の効果を誇ります。
※フロントラインはフィラリアに対しての効果はないようです。
ただ、効果が強いため一般のドラッグストアやペットショップでは置いていません。(少なくとも私は見たことありません。)
購入したい場合は、ネット通販か、動物病院でしてもらうことになります。
また、ノミやダニに対しては、駆除の効果がありますが、蚊に対してはそうではありません。
蚊自体を寄せなくするわけではなく、あくまでフィラリア予防になるというだけなので、その点はご注意を。
外を散歩する猫ちゃんなどの場合は、フィラリア感染の危険性もかなり高いため、こういった予防薬を使うことをおすすめします。
もし気になるようであれば、一度獣医さんに相談に行ってみてください。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
蚊対策グッズ
蚊よけグッズに関して、皆さんが気になるのが「通常の蚊取り線香や蚊よけスプレーなどを、猫がいる部屋でも使っていいのか?」と言うことではないですか?
調べていて分かったのですが、猫用の蚊よけグッズも通常の製品にも、大抵「ピレスロイド」という殺虫成分が使用されています。
それでは、このピレスロイドが猫に害があるかというと、無害だそうです。
以下、各蚊よけグッズを出しているメーカーへのリンクです。
※アースシリーズ猫のいる部屋での使用について【アース】
※蚊がいなくなるスプレーに関しての注意(猫に関しての記載あり)【キンチョー】
ただ、やっぱり化学製品を猫がいる部屋で使うことに抵抗がある方も多いかと思われます。
そういった場合は、化学製品を使わない電子蚊よけグッズがおすすめになります。
また、蚊よけグッズとして最も有名な蚊取り線香は火を使うため、なるべく避けた方が無難でしょう。
仮に使うとしても、猫の手の届かない部分での使用が望ましいです。
【種類ごとに紹介】猫がいても使える蚊対策グッズ
ここからは、カテゴリごとにいくつかの蚊対策グッズをまとめておきます。
分類すると、大きく3つの種類に分けられます。
- ピレスロイド配合蚊対策グッズ
- 電子機器タイプ(補虫灯など)
ピレスロイド配合蚊対策グッズ
まずは化学成分「ピレスロイド」を配合している蚊対策グッズです。
化学成分使用の殺虫剤を使う場合はなるべく、猫を別室に移す、換気をする、などした状態で使用するようにしましょう。
また、メーカーは問題ないと言っていますが、万が一猫が舐めてしまったり、直接かけてしまった場合は、洗い流したりすぐに獣医さんに診てもらうようにしましょう。
★蚊がいなくなるスプレー

抜群の効果を誇る蚊対策グッズです。
使用の際は、猫にかからないように、また換気は必ず行うようにしましょう。
★アースノーマット

蚊対策グッズとして最も有名な商品ですね。
スイッチのオンオフで簡単に使用を切り替えることができるため、蚊が特に気になる夜だけ使うこともできます。
★アースノーマット電池式
アースノーマットは様々な種類がありますが、乾電池式のものが個人的にはおすすめです。
猫が手の届かない場所などにも設置できたり、コードを噛まれる心配がなくなります。
★火を使わない蚊取り線香

蚊取り線香が好きな方は、日を使わないタイプのものもあります。
ただ、ここまで紹介してきた商品と比べると、若干効果は薄いでしょう。
アース・ペット 薬用アース ノミ・マダニとり&蚊よけ首輪 猫用

首輪タイプの蚊よけグッズもあります。
私宅でも1年ほど前に使用していましたが、正直効果を実感できたかというと、微妙な部分ではあります。
電子機器タイプ
化学製品を使うのが不安な場合は、電子機器を使うのも一つの手です。
電子機器の場合も同じですが、使用の際は猫がいじらないように使用方法や設置場所をよく考える必要があります。
殺虫ライト

特定の光源に誘い込まれた蚊が電熱で駆除されます。
猫の手などは入らないほど隙間は小さいですが、気になる方は紐で吊るすなどすると良いでしょう。
蚊取り器 蚊ランプ UV光源吸引式捕虫器

紫外線に誘い込まれた蚊が、ファンによってかごの中に吸い込まれます。
電熱なども使わないため、一番安心設計かもしれません。
ただ、あくまで吸い込むだけなので、かごを開ける際に生きてる蚊がいると出てきてしまうようです。
レビューでは、かごを開ける前に殺虫剤を一回プッシュすることをおすすめしている方もいました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
猫も蚊に刺されるし、まれに深刻な事態を招くこともあります。
特に6~9月頃(梅雨~夏の終わりごろ)は、蚊が本格的に増えるシーズンです。
気になる方は是非対策をされてみてはいかがでしょうか?
また、蚊がいる時期は熱中症などにも気をつける必要があります。
あまり対策をされていない場合は、下記記事を読むと良いかもしれません。