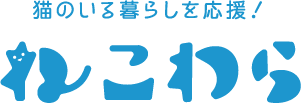あなたの家のソファや壁は、爪とぎによってボロボロになっていませんか?
もしあなたが飼い猫の爪とぎで悩んでいるのなら、爪とぎのしつけをする必要があります。
飼い猫の爪とぎ被害は、「正しいしつけをしてあげること」と、「魅力的な爪とぎ器を用意してあげること」で劇的に改善されます。
今回はそんな正しいしつけの仕方を理解することで、爪とぎ被害の対策をしっかりするようにしましょう。
爪とぎの種類についてはこちらのページから確認できます。
猫が爪とぎをする理由

猫が爪とぎをする理由は、下記2点が挙げられます。
- 古くなった爪の外層を剥がし、新しくて鋭敏な爪を露出させるため
- 縄張りにしるしをつけるため(マーキング)
猫は古来よりネズミなどを狩りすることで生きてきました。
狩りをする際に、爪は最も大切な武器になります。
そのため猫は本能的に、爪は常に鋭敏な状態にしておくという癖を持っているのです。
また爪とぎをすることで自身の匂い付けや、引っかき傷を付け縄張りアピールをするのです。
どちらも古来からの習性のため、爪とぎを止めさせるのは難しいと理解してください。
では愛猫が家具などで爪とぎをしてしまっているのを、見過ごすしかないかというと、そうでもありません。
大切なのは「正しいしつけをすること」と「猫が気に入る爪とぎを用意してあげること」です。
そうすることであなたの猫も可能な限り、適切な場所(爪とぎ)のみで爪を研ぐようになります。

爪とぎの防止・対策

基本的な爪とぎのしつけ方
まず猫の気に入っている部屋の中央に爪とぎ器を設置します。
爪とぎ器を設置する際のポイントは、猫が手を伸ばした際の高さに爪とぎ器を設置することです。
爪とぎは爪を鋭敏にする以外に、縄張りアピールの意味も持っています。
そして猫はマーキングを高いところでする習性を持っています。
なぜできるだけ高い場所で爪とぎをするかというと、高いところで爪とぎをすることで、自分を大きく見せる目的があるからです。
爪とぎ器を設置したら、その爪とぎ器に猫の前足を当て、爪を研ぐように動かしてあげてください。
そうすることで、設置した爪とぎ器に匂いがつき、自然とそこで爪とぎをするようになります。
そして猫がこれを使い始めたら、徐々に目立たない場所へ移動させます。
最終的には、猫の寝床の近くに爪とぎ器を移動させましょう。
コツは猫が適切な場所で爪とぎをしていたら、言葉をかけて撫でてやったり、ご褒美でおやつをあげたりすることです。
そうすることで、猫も爪とぎ器を継続して使うようになります。
キャットタワー付属の爪とぎなどは、高さも程よく、猫にとって魅力的な爪とぎになりやすいのでおすすめです。
また現在爪とぎを家具で行っている場合は、その家具の前に爪とぎ器を設置してください。
そして猫がそこで爪とぎをするようになったら、徐々に家具から離し目立たない場所へ移動します。
猫は関節が痛いときには、爪とぎ自体をしなくなります。
そのため、あなたの猫が全く爪とぎをしないときは、病院に連れて行ってあげましょう。
タイプ別爪とぎ器の種類
爪とぎ器は大きく分けて4種類に分類することができます。
- 紙タイプ
- 布タイプ
- 麻縄タイプ
- 木板タイプ
それぞれ色々な特徴がありますが、あなたの猫が好きな物を探ってみてください。
爪とぎ器の種類ごとにどんな特徴があるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
しつけがうまくいかない場合
しつけが思うように上手くいかない場合は、手術で爪を抜くことは一応できますが、全くおすすめではありません。
猫の大切な道具を取り上げてしまいますし、粗相などの問題行動が増えることが統計から分かっています。
何よりめちゃくちゃ痛いですしね。
大切な爪を取り上げられてしまうことで、かなりのストレスがかかることも容易に想像できます。
そのためどうしても爪とぎのしつけが上手くいかないときは、「ネイルキャップの装着」を考えてみてください。
この手段を用いることで、家具への爪とぎ被害はほぼなくなります。
ただ爪を抜くほどではないにせよ、猫にとって多少のストレスを強いることなので、なるべくは爪とぎトレーニングをする方向で考えた方が良いでしょう。
ネイルキャップについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を確認してみてください。
また最後に爪とぎをしているからといって、爪切りをしなくていいわけではありません。
完全室内飼いの猫ちゃんならなおさらです。
爪切りに関しても、正しい知識を身につけましょう。