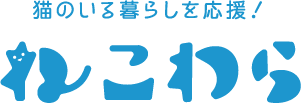猫の噛み癖は放置しておくと相手にするのが大変になってきます。
子猫のときは少し痛いくらいで済みますが、体も大きくなって力も強くなると頻繁に噛まれることで腕もボロボロになってしまいます。
今回は猫の噛み癖を直すためにどうしたらいいのかを紹介していきます。
※私の飼っている、噛み癖がとても強い猫に効果があったしつけ方を知りたい方はこちらをどうぞ!
目次
猫の噛み癖の原因から考える治し方としつけ

猫の噛み癖の原因
猫の噛み癖は本当に痛いですよね。
向こうが遊び半分にやっているように見えても、こっちとしてはかなり痛いです。
噛み癖のしつけで大切なのは、どんなことが原因で噛んでくるのかをしっかりと理解してあげることです。
噛み癖の原因として考えられることとそれぞれの直し方を解説していきます。
- 単にじゃれてるだけ
- 狩りのトレーニング
- 無防備すぎると思ったから
- 触られたくない場所を触られたから(ストレス)
- 歯がかゆいから
叱るときは「コラ!」もしくは「ダメ!」などの短い言葉で統一しましょう。
叱るときの言葉が長かったり、コロコロ変わると猫は覚えられません。

噛み癖の原因から考える治し方
単にじゃれてるだけ
猫の噛み癖の原因の一つは単純にじゃれてる際に、テンションが上がって噛んでしまうということです。
元々猫はどれくらいの力で噛むと相手が嫌がるかなどを、兄弟猫など他の猫と共にいる子猫の期間に学習します。
ですが、そういった経験が薄い猫の場合、単にじゃれるだけでもかなり強い力で噛んでくることがあります。
そういった猫に対しては、噛まれたらスッとその場を去るようにしましょう。
あなたの腕を噛む=構ってもらえなくなると覚えてもらうのです。
また噛み癖と同様に蹴り癖を持っている場合もあります。
猫のキックを止めさせる方法はこちらから確認できます。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
狩りのトレーニング
噛みつきは狩りのトレーニングとして行われていることもあります。
狩りのトレーニングとしての噛み癖を持っている場合はじゃれてる場合の直し方と同じです。
噛みつく=構ってもらえなくなると覚えてもらうことが大切です。
また狩りのトレーニングとして噛まれてしまっている場合は、腕をおもちゃの一つとして思われないようにすることも大切です。
猫じゃらしやネズミじゃらしを使って、狩りのトレーニングをさせてあげましょう。
無防備すぎると思ったから
猫を撫でている時に、とてもリラックスしていた猫が急に噛んできたことはありませんか?
そういった猫は防衛本能から噛んでしまっていることが考えられます。
基本的に撫でられて嫌がらない猫は、子猫のような気持ちで身を許しています。
守られて、注目も集めてリラックスしていますが、急にそんな自分の態勢が無防備に感じられてしまうのです。
そうすると猫はすぐに自分の身を守るために人を噛んだり、攻撃性を見せた行動を起こします。
そしてその後すぐに自分をリラックスさせるため、飼い主さんから少し離れた場所に行ってグルーミングし始めるのです。
こういった場合の対処法としては、猫を触る時間を頻繁に、そして短くすることが望ましいです。
そうすることで噛まれず撫でてあげることができます。
触られたくない場所を触られたから
ほとんどの猫は敏感な部分を触られるのが苦手です。
具体的にはお腹や足の先っぽ、しっぽなどです。
こういった場所を触ると怒る場合は、特定の部位を触らないように注意しましょう。
また何か猫にとってストレスが溜まるような行動をしてしまっている時も噛まれることがあります。
猫にとってストレスが溜まることはこちらから確認できます。
思い当たることがある場合は直すようにしましょう。
歯がかゆいから
子猫の噛み癖は、歯がかゆいからという理由も考えられます。
猫は生後1カ月程度で乳歯が生え揃いますが、乳歯が永久歯に生え変わるまではムズムズしてしまうそうです。
永久歯に生え変わるのは生後4カ月~7カ月目までなので、永久歯に生え変わるのを機にぴったりと噛み癖がなくなることもあります。
幼猫の中には、口がムズムズするためコードを噛む癖を持っている子も多いようです。
電気が通っているコードを噛むと感電してしまう恐れもあるため、防止策を取るようにしましょう。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
まとめ
噛み癖にもいくつかの原因があります。
それぞれの原因ごとに対処法も変えていきましょう。
よくある原因としては以下の5つになります。
- 単にじゃれてるだけ
- 狩りのトレーニング
- 無防備すぎると思ったから
- 触られたくない場所を触られたから(ストレス)
- 歯がかゆいから
どうしても直らない場合は、かかりつけの獣医さんに相談するのもひとつの手です。
また本気噛みではなく、愛猫が甘噛みをしてくる場合の理由と対策はこちらから確認できます。