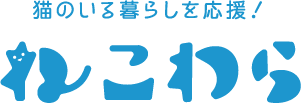猫は泌尿器系の病気にかかりやすい動物です。
尿路結石などと共に膀胱炎は、特に発症しやすい病気の一つと言えます。
現在猫を飼っている方などは是非確認してみてください!
実際、私は愛猫わたげの膀胱炎治療に、40万円の治療費を払いました。
その時の体験談を読みたい方はこちらをどうぞ。
目次
猫の膀胱炎とは
膀胱炎とは膀胱が炎症を起こしてしまう病気のことを言います。
ひとえに膀胱炎と言っても大きく2つの膀胱炎に分けることができます。
- 特発性膀胱炎
- 細菌性膀胱炎
特発性膀胱炎とは簡単に言ってしまうと、原因がハッキリしていない膀胱炎のことです。
ただストレスが強く関係していると考えられています。
細菌性膀胱炎とは主に猫の尿道から細菌が入ってしまい、その細菌が膀胱にて炎症を起こしてしまう病気のことです。
大抵の場合、細菌とは大腸炎のようです。
当ページで紹介している膀胱炎や「尿路結石」など泌尿器系の病気のことを総称して、下部尿路疾患(泌尿器の中の膀胱から尿道までのこと)と呼びます。
下部尿路疾患の割合は以下のようになっています。

一目で分かる通り、特発性膀胱炎が半数以上を占めています。
特に1~10歳程度の若い猫が特発性膀胱炎にかかりやすいようです。
続いて膀胱炎持ちの猫が出すサインを紹介していきます。
猫の膀胱炎の症状チェック!
猫が膀胱炎になっている場合は何かしらのサインが出ています。
なかなか分かりにくいですが、下記のようなサインに心当たりはありませんでしょうか?
- 長い間うずくまってじっとしている
- 飲水量の増加
- お腹や下腹部をしきりになめている
- トイレにいる時間が長い
- トイレで鳴き声を上げる
- トイレ以外の場所での排尿(粗相)
- 食欲不振
- 血尿
- おしっこがいつもより臭い
- おしっこがいつもより濃い
上記の症状に心当たりがある場合は、何かしら膀胱炎など泌尿器系の病気にかかっている可能性が高いと言えます。
すぐにかかりつけの獣医さんに診てもらいましょう。

猫の膀胱炎の原因と予防方法は?

膀胱炎の種類ごとにどんな原因があるのかを紹介していきます。
また膀胱炎を起こさないための予防についても同時に紹介していきます。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
特発性膀胱炎の原因と予防方法
特発性膀胱炎は原因こそ詳しく分かりませんが、ストレスや肥満、寒さなど様々なものが影響していると考えられています。
ただ特発性膀胱炎になりやすい猫の種類として神経質な猫が挙げられることから、やはりストレスが大きく影響しているでしょう。
予防方法としては、普段から猫がストレスを感じないようにすることです。
例えば多頭飼いをしている場合、猫同士の仲が良くないと立場の弱い方がストレスを感じてしまいます。
また大抵の猫は環境の変化が苦手なため、引っ越しなどもストレスにつながります。
その他にも猫がストレスを感じる要因は数多くあります。
ストレスを感じるような環境になってないか確認するようにしましょう。
細菌性膀胱炎の原因と予防方法
細菌性膀胱炎の原因は尿道から入り込んだ細菌です。
ここで言う細菌とは大抵の場合は大腸菌のことです。
排泄物などがそのままになっている汚いトイレを使うことで、尿道から細菌が入ってしまうパターンが多いと考えられています。
予防方法としては、下記の2点が挙げられます。
- トイレを清潔に保つ
- 飲水量の増加
原因でもあるため分かりやすいですが、トイレをきれいに保つことが細菌性膀胱炎にかかりにくくする第一の予防方法です。
また猫砂はおよそ2週間に1回は取り換えてあげるようにしましょう。
容器自体を洗うこともトイレを清潔に保つのに大切なことです。
多頭飼いをしている場合などは、「飼っている頭数+1」のトイレを用意することをおすすめします。
続いてしっかり水を飲んでもらうことで、排尿を促します。
おしっこを頻繁にすることで、尿道から入り込んだ細菌を排出することにつながります。
ちなみに猫の平均排尿回数は1日2~3回ほどです。
おしっこに行く回数が急に変化した場合などは、一度獣医さんに様子を診てもらいましょう。
- メス猫
- 尿道を短くした(ペニスを切除した)オス猫
- 飲水量の少ない猫
- 老猫
特に細菌性膀胱炎にかかりやすい猫です。
特発性膀胱炎と違って、老猫がかかりやすいのも細菌性膀胱炎の特徴です。
猫の膀胱炎の治療について
膀胱炎に実際かかってしまった場合はどのような治療をするのでしょうか?
それぞれの膀胱炎毎の治療方法を紹介していきます。
特発性膀胱炎の治療
特発性膀胱炎は原因が分からない病気であるため、ピンポイントでの治療は難しいです。
そのため鎮痛剤などを利用して、痛みを和らげるケースが多いです。
基本的には3~7日ほどで回復するケースが多いため、自然治癒を待つという選択肢になることが多いようです。
ただ猫のストレス管理は必須になるでしょう。
注意が必要なのが、特発性膀胱炎は再発しやすいという点です。
猫の様子を普段から見ることで、猫が何に対してストレスを感じているかを理解することにつながります。
細菌性膀胱炎の治療
細菌性膀胱炎の場合、どの細菌が膀胱炎を引き起こす原因となっているか尿検査を行います。
原因となっている細菌が分かった場合は、その細菌に効果のある抗生物質を投与します。
ただ抗生物質が効かない真菌(カビ)が原因となっている場合もあるようです。
そういった場合は抗生物質ではなく、抗真菌薬で対処をすることになるようです。
「細菌性膀胱炎」と「特発性膀胱炎」以外にも、膀胱の中にできた結石が膀胱を傷つけ、膀胱炎になってしまうこともあるようです。
こういった場合もその時々で異なる治療をすることになるようです。
私の愛猫も膀胱炎になったことがある?
実は私の愛猫わたげも以前、膀胱炎になったことがあります。
※正確には尿路結石・膀胱炎・腎不全の併発。
その時は本当に、筆舌に尽くしがたいほど、大変な時間を過ごしました。
約2週間の間、毎日病院に通院するという看病体験をし、更に治療費総額は40万円を超えました。
もうとにかく大変で、精神的にも酷く落ち込んだ生活を送っていました。
その時の体験談を読みたいという方は、こちらをどうぞ。
まとめ
膀胱炎は下部尿路疾患の中でも特にかかりやすい病気の一つと言えます。
膀胱炎にかからないようにするためには、「ストレスを溜めさせない」「トイレを清潔に保つ」などが挙げられます。
猫が膀胱炎にかからないように、日頃から様子を見るようにしましょう。
また猫は膀胱炎を含む、泌尿器系の病気にかかりやすい動物です。
膀胱炎以外にどのような泌尿器系の病気があるか知っておきたい場合は、こちらをどうぞ。